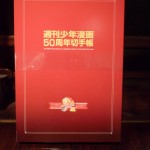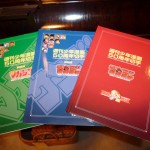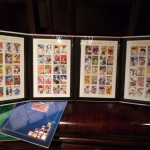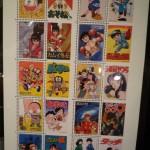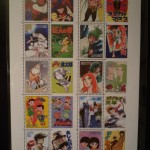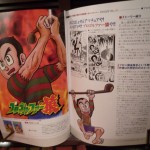micchoがこちらで紹介していた、氷見海浜植物園の「蝶とカブトムシ展」に行ってきました。
まずはクワガタ。触ることができます。

久しぶりに見たミヤマクワガタ。けんかしてますね。

こちらはカブトムシ。子供たちも自由に触れていましたが、足がちぎれていたりということはありませんでした。

温室の中にはチョウチョが放たれていました。外国産のかなり大きなチョウチョでした(名前は失念しました)。

蜜を吸っています。かなりカメラを近づけても逃げませんでした。

ちょっと休憩。氷見でしか販売されていないジェラートだそうです。植物園の売店で購入できます。

夜は、以前も紹介したきときと舎さんに行きました(こちらも)。自分の中で定番化している、串カツ、焼きそば、ポテトサラダなどを食べつつ、赤ワインを飲みました。
ポテトサラダ。かなりたっぷりしています。これと赤ワインとガーリックトーストなどをとれば、簡単な夕食になりそうです。

前回の紹介記事では、酔っぱらって撮影し忘れていた串カツです。これもどっしりとした質感。

焼きそば。くどい味付けではないので、あっさり胃に収まります。

今回出してもらった赤ワイン。南アフリカの “KOELENBOSCH” という銘。まろやかで、ほどほどのボディーがあり、どんな料理にも合いそうです。

赤ワインのアテとして出してもらった、チーズの盛り合わせ(フラッシュが強すぎて、白く画像が飛んでしまってますが…)。右側に写っている、クラッカーにクリームチーズを塗り、プルーンをのせたものが美味しかったです。