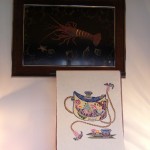先週より、ラローチャのショパンを流しています。昨年より、ずっとヴァイオリンがBGMだったので、久々にじっくりピアノが聴きたくなりました。しっとり厳かな音色、お楽しみ下さいね。
-
-
裏管理人独白:「悪徳の勧め」
裏管理人です。日曜はこのサイトの通常の更新がない日ですので、その機に乗じてちょっとだけ書いてみます。
先日の朝日新聞の夕刊に、経済学者で東京大学教授の岩井克人さんが、「悪徳の勧め」というちょっと面白い表現を使って、昨今の停滞している経済状況に関して、提言をしています。
岩井先生は、まず経済学者ケインズによる「不況」の定義を紹介してくれます。
不況とは、人が本来商品を買う「手段」であるお金を、将来への不安に備え、商品より欲しがって貯め込んでしまう状態だと、いったそうだ。お金さえあれば安心だと。で、物が売れないから売り手は値段を下げる。でも売れない。この状況をお金を貯めている側から見ると、お金の価値が上がることになるため、ますます貯め、また売れなくなるという悪循環。
今のデフレ状態は、まさにこのケインズが定義する状況とぴったり符合しますね。各業界の一部の企業が、熾烈な価格戦争の中で商品やサービスの値段を下げることによって、「勝ち組」となっているわけですが、多くの経済学者や有識者が指摘している通り、長い目で見ればこの状況は、完全に自分の首を絞めていることにしかならないわけです。貯め込まれることで、お金は流れなくなってしまうと、最終的には「勝ち組」の商品やサービスも売れなくなり、結果的に自滅へと向かうのですから。
岩井先生は、このような状態においては、各種のセーフティーネットの創設はもちろん必要だが、「悪徳の勧め」も必要だと述べています。
質素、倹約に努めるという個々人の美徳的な行動が、まとまれば結果として、さらに人々の生活を脅かすものになる。昔から多くの経済学者が指摘していましたが、浪費や美食などの多少の悪徳を許して経済を刺激しないと、経済は生きていけないのです。
「悪徳」という言葉に差し障りがあるならば、「心の余裕」とでも置き換えてもいいのかもしれません。今の日本の経済状況は、無駄な脂肪がない筋肉質の身体を通り越して、飢餓状態で骨と皮だけの身体になりつつあります。でも、一方でお金は万が一のために貯め込んでいる。お金は貯めているけれども、それを使わずに、自らを飢えへと追いやっているような状態です。岩井先生の言う「悪徳」とは、このような経済的身体に与えるべき「食べ物」だと言ってもいいでしょうか。お金を「食べ物」に交換することで、お金の流れが生じ、停滞が改善されていく一助となるのです。
長く続く倹約生活には気持ちも荒んできます。自分を励ます意味で、「悪徳」をちょっぴりかじってみてはいかがでしょうか。
岩井先生の『ヴェニスの商人の資本論』は面白いですよ。シェイクスピアの有名な『ヴェニスの商人』を、経済学の視点、特に「交換」という概念からダイナミックに解釈した論が巻頭に収められています。
-
成人の日営業しております
1月11日(月・祝日)の成人の日も営業しております。みなさまのご来店をお待ちしております。
-
紅白歌合戦に思う
少し前の話題になりますが、昨年の大晦日も紅白歌合戦を愉しみました。歌手の皆さんの衣装が気になるんですよね。やっぱり着物が。今回は、着物、帯そのものよりも、帯揚げ帯締め、重ね襟の色遣いが非常に大きな役割を果たしているということを改めて実感しました。いいなと思ったポイントを、私なりに挙げてみます。
まずは、司会の仲間由紀恵さんがオープニングで着ていた友禅の振袖コーディネート。疋田絞りの帯揚げが効いていました。視覚的に、友禅は平面的、絞りは立体的です。友禅の着物を纏う場合、帯揚げに絞りを持ってくることで、着物と帯の間に立体感ができ、コーディネートにメリハリがつきます。特に、振袖のようにボリューム感を出して華やかに演出する場合、この平面+立体コーディネートは、覚えておくといいでしょう。
それから、演歌歌手の皆さんの着こなしですが、全体を通して重ね襟、帯締めにブルーや紺を合わせるコーディネートが多かったように思います。ステージに立つ場合、盛装の場合、迷ったら「青」というのは、当店でもよくお客様にオススメしているやり方です。青系は、意外と何色にもいけるんですよ。パッと華やかな印象に変えたり、キュッと引き締め効果を出したり、お助けカラーです。
そして、石川さゆりさんのお着物姿がやはり素敵でした。白地にブルーの飛び柄、小袖模様の帯。帯締めは濃紺でビシッと。古典的でモダンで、垢抜けた着こなしでした。さゆりさんの内側にあるクオリティと、身に付けているもののクオリティが、ぴったり合っているんですよね、いつも。つまりそれが、本当に「似合っている」とか「着こなしている」ということなのですが、石川さゆり像は揺るぎないですね。
今月は、成人式や初釜、新年会と和装のシーンがたくさんあります。小物で大きく印象が変わるコーディネート、じっくり考えて愉しい着物の時間をお過ごしくださいませ。
-
ご来店ありがとうございました
昨日は、今年最初の営業日でした。たくさんのお客様にご来店いただき、縁起の良いスタートとなりました。皆さま、ありがとうございました。
さて、今年の年賀状ですが、着物は辻が花の訪問着、帯はひなや製組み紐の袋帯という組み合わせでした。昨年より二階に展示しておりましたところ、皆さまより大好評をいただきました。訪問着の作家は実力派、小野順子さん。女性らしい優しく上品な作風が特徴です。
-
J. S. Bach と光悦ー元日クラシックコンサートー
さて皆様、元日はいかがお過ごしでしたでしょうか。私は京都ハイアットリージェンシーホテルにて行われました、クラシックコンサートを聴くチャンスに恵まれました。ただのコンサートではありません。音楽と着物のコラボレーション。同じ時代に西洋と東洋で存在した音楽の父バッハと、琳派の創始者である本阿弥光悦、ふたりの残した文化の軌跡を同時に体感できる企画でした。ホールに入ると、光悦時代の代表的な文様を、染め、織り、絞り、様々な技術で表現した着物や帯が展示されており、コンサートまでのひと時を和のモードでゆったりと過ごせます。
いざコンサートの開始です。今回は、バッハの時代にピアノは存在しなかったということで、チェンバロが用意されました。初めて聴く繊細な音色は、今でも耳に残っています。第一部では、ヴィヴァルディの四季を春夏秋冬とおして聴くことができました。しかも、解説付きです。例えば、春では小鳥のさえずりが楽譜に書き込まれているのですが、まず、さえずりの部分だけを聴かせてもらい、演奏に移るという段取り。クラシックは好きでしたが、今までは音としてだけ捉えていたので、きちんと音の表現する意味やドラマを教えてもらえたことが、とても嬉しく新鮮でした。秋の場面では、収穫の秋ということで、祝宴をする人々の中に酔っ払いがいて、その気持ちよく千鳥足になっている様子を表現した音がありました。面白いですね。こういうことを、ひとつでも多く分かっていたら、精神的にとても豊かになれるのだろうと思います。演奏中にずっと感じていたことは、音楽も着物も同じだということ。楽譜に小鳥のさえずりが書き込まれているのと同じように、着物にはその時代や文化を象徴する文様が表現されています。着物は、読み解くものでもあるということを、強く感じました。
さて、この素敵な企画に関わっていらした藤井絞の社長さん。縁起のひょうたんなまずの羽織でお越しでした。男性の羽織は、いろいろに遊ぶことができて本当に愉しみですね。